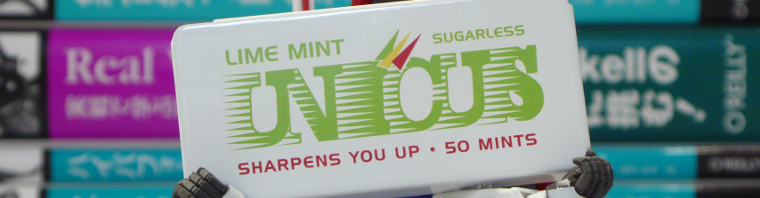CppUnitをWindowsでも使うことになってビルドを試みたのだけれど、結構ハマったので、ビルド方法をメモっておくよ。
WindowsでCppUnit使いたいのだけれど…
■C++アプリケーションの効率的なテスト手法(CppUnit編) - @IT
ここを参考にMicrosoft Visual Studio VC++でビルドをしてみた。
- VC++ 2010 Express プロジェクトファイル(.dsw)変換に失敗
- VC++ 2008 Express リンクエラーでビルド失敗
となって、うまくいかない・・・
試行錯誤の結果、うまくビルドできたので以下手順を説明するよ。
準備
以下のものを用意する
VC++は別々のディレクトリにインストールされるので共存できるよ。
ビルド手順
cppunit-1.12.1.tar.gzはあらかじめ解凍ソフトなどで解凍しておく。
VC++ 2008でCppUnitTestMainプロジェクトを開く
●VC++2008を起動
●「ファイル」→「開く」→「プロジェクト/ソリューション」
cppunit-1.12.1\examples\cppunittest\CppUnitTestMain.dswを選択
(cppunit-1.12.1\examples\cppunittest\CppUnitTestMain.dspでもよい)

プロジェクトの変換
●「変換してこのプロジェクトを開きますか?」と聞かれるので「すべてはい」
VC++2010じゃなくてVC++2008で使いたい人は→後述へ飛ぶ

プロジェクトの依存関係を外す
●「プロジェクト」→「プロジェクトの依存関係」
プロジェクト「CppUnitTestMain」を選択し、依存先のcppunit、cppunit_dllに入ってるチェックを外して「OK」

ソリューションファイルの保存
●ソリューションエクスプローラで
「ソリューション ‘CppUnitTestMain’ (3プロジェクト)」と書いてあるところを選択して、「ファイル」→「CppUnitTestMain.slnを保存」
ソリューションエクスプローラが見つからないときは「表示」→「ソリューションエクスプローラ」
●「ファイル」→「終了」でVC++2008の役目はこれでおしまい。
VC++ 2010でCppUnitTestMainプロジェクトを開く
●VC++ 2010を起動
●「ファイル」→「開く」→「プロジェクト/ソリューション」
cppunit-1.12.1\examples\cppunittest\CppUnitTestMain.slnを選択

VisualStudio変換ウィザード
自動的にウィザードが起動する。基本的に全部そのまま「次へ」でOK
●バックアップ作成の選択「変換前にバックアップを作成する」を選択すると.oldをつけたバックアップが作成される。
再びVC++2008で開きたいときなどに必要になるよ。

●「変換の完了」が出たら「閉じる」。「ウィザードが閉じたとき変換ログを表示する」にチェックが入ってると変換レポートが表示される。
プロジェクトのプロパティ設定
cppunit,cppunit_dllプロジェクトについて確認すべき点は2点。
- 「構成プロパティ」→「全般」→「ターゲット名」
- 「C/C++」→「コード生成」→「ランタイムライブラリ」
これらに気をつけて各プロジェクトのプロパティを以下の表のように設定する。
| プロジェクト |
構成 |
ターゲット名 |
ランタイムライブラリ |
| cppunit |
Debug |
$(ProjectName)d |
マルチスレッドデバッグ(/MTd) |
| Release |
$(ProjectName) |
マルチスレッド(/MT) |
cppunit_dll |
Debug |
cppunitd_dll |
マルチスレッドデバッグDLL(/MDd) |
| Release |
$(ProjectName) |
マルチスレッドDLL(/MD) |
| CppUnitTestMain |
Debug |
$(ProjectName) |
マルチスレッドデバッグ(/MTd) |
| Release |
マルチスレッド(/MT) |
DebugDLL |
マルチスレッドデバッグDLL(/MDd) |
| ReleaseDLL |
マルチスレッドDLL(/MD) |
プロジェクト依存関係の設定
「プロジェクト」→「プロジェクトの依存関係」でCppUnitTestMainプロジェクトを選択、
依存先
にチェックを入れてOK。

バッチビルドの実行
●「ツール」→「設定」→「上級者用の設定」を選択
メニューバーに「ビルド」項目が現れる
●「ビルド」→「バッチビルド」→「すべて選択」→「ビルド」
一度「クリーン」してから「ビルド」すると安心かもね。

DLL版はコンパイル中にC4251のwarningが結構出るけど特に問題ないと思う。
CppUnitTestMainがビルドできると、自動でテストの実行も行ってるよ。
●8つの全部が正常終了すればOK。
CppUnitを使ったプロジェクトを作るときにはCppUnitTestMainのプロパティを参考に設定するといいよ。
うまくいかない?
設定をもう一度見直してみよう。とくにランタイムライブラリの設定だね。
VC++2008でプロジェクトの依存関係を外さずにCppUnitTestMain.slnを保存してしまった場合は、
VC++2010でこれを開くと「プロジェクト」→「プロジェクトの依存関係」から編集ができなくなるよ。
CppUnitTestMainの「共通プロパティ」→「Frameworkと参照」ですべての「参照を削除」すれば編集できるようになるよ。
VC++ 2008でビルドしたいんだよ
って言う人は、上記手順のCppUnitTestMain.dswを開いた後、「プロジェクトの依存関係」は外さずに、
CppUnitTestMainのプロパティで
「リンカー」→「全般」→「リンクライブラリの依存関係」をすべての構成(Debug,Release,DebugDLL,ReleaseDLL)で「いいえ」に設定。
これをいいえにしないと、プロジェクト依存関係にあるcppunit,cppunit_dllのどちらもリンクしようとして競合して失敗する。
リンクライブラリの依存関係を「はい」のまま、プロジェクトの依存関係を外して、先にcppunitとcppunit_dllをビルドしておいて、CppUnitTestMainを単体でビルドするとうまくリンクできるはずだ。
あとは上のVC++ 2010のプロパティ設定の表のようにランタイムライブラリを適切に設定する。ターゲット名は修正しなくてよい。

(以下追記 2011/04/16)
ていうか、プロジェクトファイルくれよ
というリクエストがありました。ですよね。欲しいですよね。
cppunit-1.12.1 の Microsoft Visual Studio C++ 2010 Express用プロジェクトファイル
cppunittest-1.12.1-vcxproj.zip
↑このzipを展開すると、以下の7つのファイルが入ってるよ。
examples\cppunittest
- CppUnitTestMain.sln
- CppUnitTestMain.vcxproj
- CppUnitTestMain.vcxproj.filters
src\cppunit
- cppunit.vcxproj
- cppunit.vcxproj.filters
- cppunit_dll.vcxproj
- cppunit_dll.vcxproj.filters
この4つをcppunit-1.12.1以下の対応するディレクトリに置いてCppUnitTestMain.slnをダブルクリックで起動すればそのまま使えるはず。
ちなみにVisual Studio C++のProfessional版なら、上の手順みたく頑張らなくてもプロジェクトファイル変換できたよ…